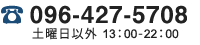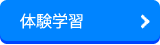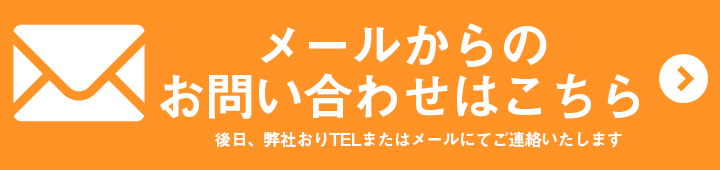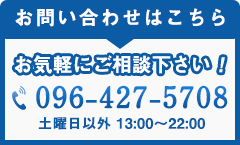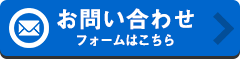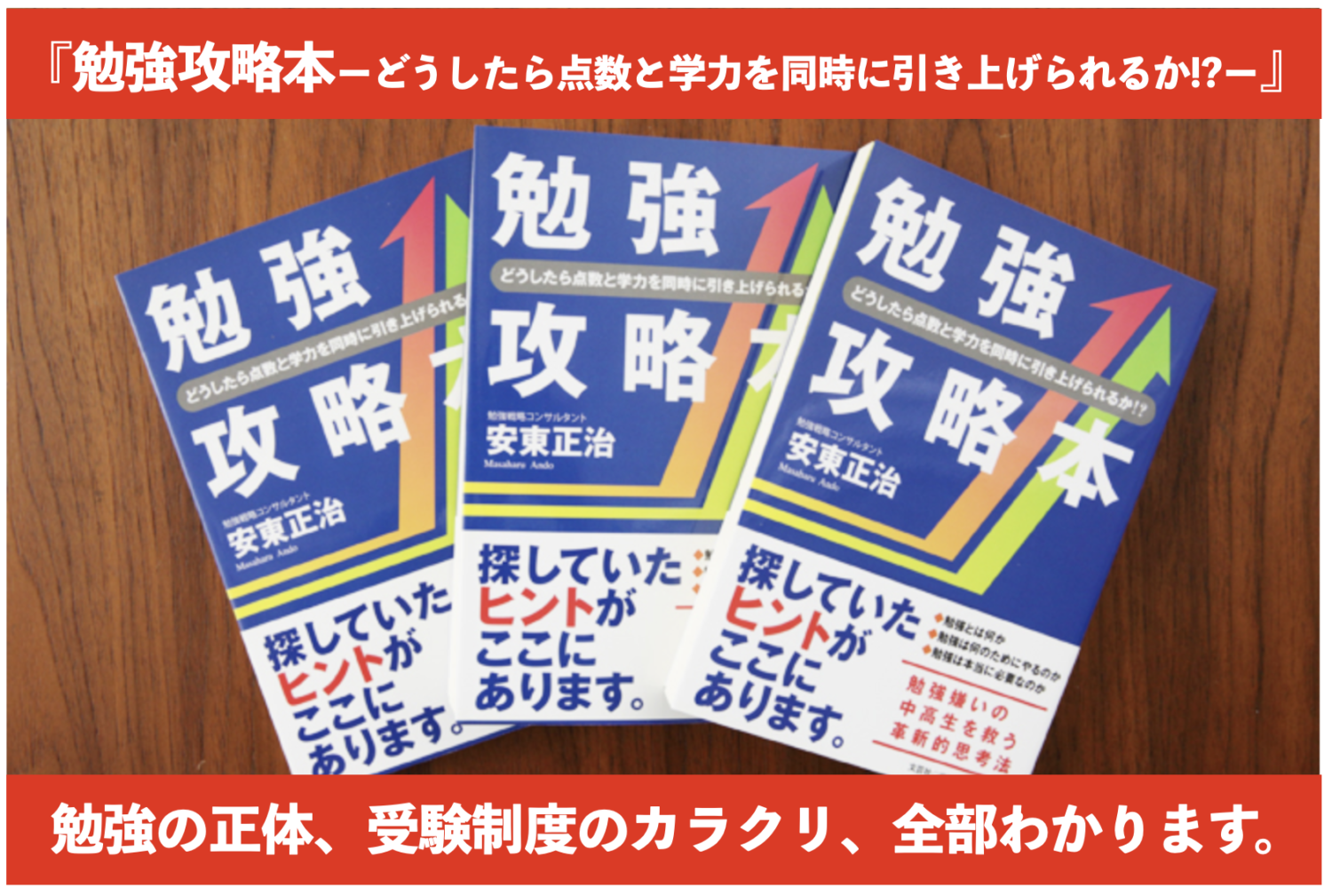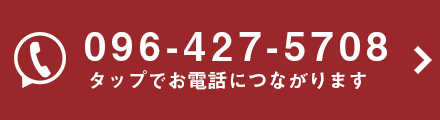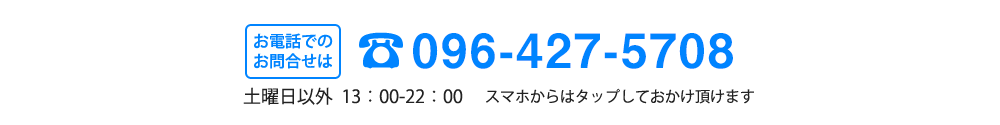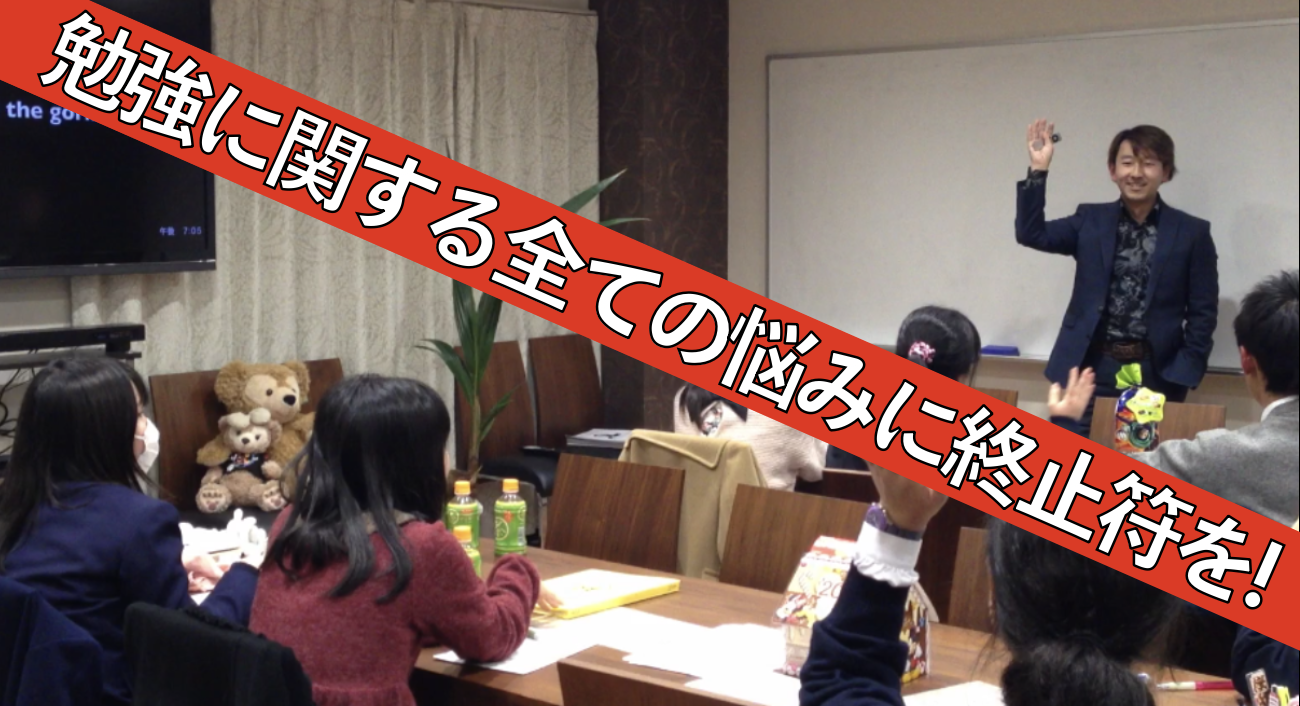電子書籍『勉強のルール -もうこれ以上、勉強の犠牲になるな。-』出版告知|熊本の学習塾ブレイクスルー・アカデミー
こんにちは。熊本の教育&勉強攻略アドバイザー、ブレイクスルー・アカデミー代表の安東正治です。
今回の記事では、先日登壇させていただいた『オンライン講演会2023 通信制高校からの大学進学』登壇記念に書き下ろした最新著作『勉強のルール-もうこれ以上、勉強の犠牲になるな。-』を出版致しますので、その告知をさせていただきます!
前作『勉強攻略本-どうしたら点数と学力を同時に引き上げられるか!?-』から早12年。完全ゼロからの執筆となりました。その分、今の私の思いの丈を全てこの1冊に込めました。勉強に関して言いたいことは全てこの中に入れられた、、、わけではありませんが、少なくても言いたいことの触りは全て、この1冊に込め切った感じです。1つ1つの項目で、より詳細な情報をお求めの方は是非私に直接お問い合わせ下さい。あなたに必要なことは、あなたにしか分からないので、この本の中で刺さった内容でもっと詳しく聞きたいことは、是非直接私に投げかけて下さい。真剣にお答えさせていただきます。
さて、そこで今回は、冒頭の[はじめに]の部分と[もくじ]を無料で公開させていただきます。正直[はじめに]だけでもかなりのボリュームがありますので、それだけでもご満足いただけてしまうかも知れませんが、本番はその先にあります。今現在270,000円(+税)でご提供させていただいている「独学術マスターコース」の教科書として、今後活用する予定です。本コースは、この本の中に書かれていることを、1つ1つさらに詳しく解説していくものですので、それを考えると今回の本はかなり重要なところまで踏み込んで書き上げてしまいました(笑)こちらのサイトに立ち寄って下さった方については、さらにこちらから400ページ以上の内容の全てを無料で閲覧いただけます。もし、本記事の先も気になる!という方は、是非全文に目を通していただけたらと思います。
Contents
『勉強のルール』[はじめに]


日本の教育は今、変革期を迎えています。
「誰一人取り残さない教育」を合言葉に、2019年からのGIGAスクール構想(Global and Innovation Gateway for All(全ての児童・生徒のための世界につながる革新的な扉))にはじまり 、2020年には教育改革によって、英語教育改革、プログラミング教育、アクティブラーニング、大学入試制度改革等が矢継ぎ早に実施され、教師や生徒だけでなく企業、社会を巻き込んだ一大改革が進められています。
ではなぜここまで急激な変革が余儀なくされているのか。それは日本の教育システムが完全に行き詰まり、時代の要請に足る人材育成が十分成し得ていないという危機的状況があるからです。特にイノベーション創出のための高度理系人材の確保という点で言えば、デジタル社会に急速に移行していく世界の趨勢から考えると、かねてより優先的な課題であったにも関わらず、今では完全に他国の後塵を拝しています。日本で一体何が起きているのでしょうか。
日本人は本来学力の高い国民です。江戸末期、鎖国状態にあった日本はたった4隻の黒船来航で強制覚醒させられて開国に踏み切りました。1868年の明治維新です。しかしそこからの追い上げは凄まじかった。日本はたった30年で一気に、当時の大国イギリスと対等な同盟(日英同盟)を結べるまでになり、眠れる獅子と恐れられた清を蹴散らし、無敵と言われたロシアのバルチック艦隊を海に沈める”大国”へとのし上がりました。
その後第二次世界大戦で敗戦を喫した帝国主義国家は、GHQ占領下でWGIP(War Guilt Information Program)はじめ、日本国憲法や教育基本法等の起草に介入を許すなど大いに牙を抜かれながらも、焦土と化した自国を見事に復興させ、1955年から1973年の19年間で年平均10%の経済成長という高度経済成長期を創出。そして1986年12月から始まるバブル景気で日本はピークを迎えることになります。『SLAM DUNK』の湘北山王戦を彷彿とさせる底力と粘り強さです。飲めや歌えやの狂乱日本の隆盛は、絶頂期には山手線内側の土地価格でアメリカ全土が買えると言われた程でした。こういう時代が確かに日本にはあったのです。。。
それから間もなくしてバブルは崩壊。一気に経済がシュリンクした日本のその後30年間、全く生産性を上げられないまま現代に至ります。経済成長率1%未満。高度理系人材の圧倒的不足。かつては1位だったIMD世界競争力ランキングでは、2023年版で過去最低の35位という惨状。
こうした、生産性の低下、低迷したままの経済、人材の不足、超高齢化、そして少子化等を背景に持つ日本が、再び世界と伍して振る舞うための喫緊の課題として、今「人材育成」にフルコミットすることが求められている。それが日本の教育制度改革の前提です。
それでは、そこで育成される人材、子どもたちにフォーカスしてみましょう。先に挙げた大人たちの認識とは完全に乖離した世界が、ここには広がっています。彼らの目下の関心は「勉強」という得体の知れない存在に向けられているからです。
舵を思いっきり切って、諸々をすっ飛ばした上で結論からお話させていただくと、
勉強にはルールがある
一言で言えば、これがこの本を通してあなたに伝えたいメッセージの要諦です。そのルールさえ分かってしまえば、学校の成績を伸ばすことはおろか、偏差値で進路を選ぶなんて誤った人生選択をしないで済むようになります。「自分も頑張れば医学部に合格できるだろうか!?」なんてギャンブルに大事な人生を投じる必要もなくなるでしょう。本当に必要なのは”頑張り”ではなく”努力”だと分かれば、地に足のついた状態で、勝算のある戦略を立て、合格に直結した努力ができるようになる。
これは「頑張っているのに伸びない!」と悩んできた人も例外ではありません。能力云々の話ではなく、その仕組みを理解し、ルールに則ってプレーをすれば誰でも結果が出せる”スポーツ”、それが勉強なのです。ただ1つ問題があるとすれば、そのルールを誰も教えてくれないことにあります。
そこで、この本には「勉強のルール」の全てを書き記すことにしました。が、それは先に挙げたような「英数国社理の勉強をどう進めれば効率的に成果を出すことができるのか」というテクニック論に終始するものではありません。むしろそれらは枝葉に過ぎないのであって、そこだけをどんなに詳細に話したところで問題は解決しないからです。私たちが知るべき「勉強」というテーマの”事の本質”はもっと奥にある。
「勉強」とは本来「学び」とは似て非なるものです。この、本来は別物として取り扱われるべき2つの要素が、今やメビウスの輪のように捻じ曲げられて繋がり、混同されて扱われているというのが、学校制度および学習塾業界の置かれている現状です。
当然そのせいで「教育」も迷走します。何をどうすることが正解なのかが分からないからです。今のままでは、その答え合わせに10年も20年も掛かってしまう。”今”必死に出した答えが、本当に10年後20年後の将来においても正解であり続けるのか?ということに確信が持てないからです。では、この先いつまで続くか分からないその不安に耐え続けるしか道はないのでしょうか。正にここに答えようというのがこの本の目的になります。
これまでは別に「勉強とは何か」「学びとは何か」「教育とは何か」といった話題に、そこまで明瞭な答えは求められて来ませんでした。言い方は悪いですが、何となくの理解で良かったのです。それこそ「コレなんですか?」と不思議なモノを持ってきて「え、なんだろ?」「コレ○○じゃない?」「私は△△だと思うけど」「いや、◻︎◻︎じゃないか?」なんてやり取りに終始し、結論が出なかったし、そこで議論が終わっても事欠くことはなかったからです。
しかし、その”曖昧”が許された状況に変化が起き始めました。そう、教育改革です。
急速なグローバル化、ボーダレス化、情報化、テクノロジーの進化などに加え、日本が独自に抱える超高齢社会化や少子化、それに伴う人材育成の遅れ、さらには失われた30年という経済の鈍化。世界全体の成長速度、変質変容の速度に、日本の教育体制が全く追いついていない焦りとその皺寄せが、教育改革となって今、一気に押し寄せているのです。
そんな状況が、学校教育制度の根幹を成すはずの「勉強」「学び」「教育」といった重大テーマに対する共通認識が無い上に伸し掛かってくる。とすれば、この先の展開はもう火を見るよりも明らかでしょう。
01. 備えろ
「勉強」というテーマを軸にして、そこに複雑に絡み合った「学び」と「教育」という要素を解きほぐしつつ、それらにこびり付いたありとあらゆる用語について定義を明確にしていくことで、得体の知れなかった「勉強」というものの核心に迫ること。その結果、あなたに「自分で勉強できるスキル」すなわち「問題解決能力」を身に付けてもらうこと。それがこの本の主目的となっています。
大幅な成績アップ、志望校への合格可能性の飛躍的向上。これらは問題解決能力を身に付ける過程で副次的に起こる効果であって、オマケに過ぎません。本当に大切なのは、自分で戦うための武器を手に入れ、それを使いこなす練習をすること、あなた自身が強くなることにあります。その為の手段として「勉強」を理解して下さいという、これは1つの提案なのです。
例えばこの本の中では、「勉強が単なる暗記大会であることを受け入れた上で、それにどう対処すれば効率的に成果を出せるか」という視点から論を展開している部分もあります。この点には、一方で暗記大会に過ぎない学校教育の在り方を”悪し”と見なす向きもあるため、その「受け入れて対処する」という王道アプローチを”前時代的”だと感じる人もいるかも知れません。
それはそれで間違いないのだけれど、これまでの暗記大会に過ぎなかった勉強でも優秀な人材が輩出されてきた背景を踏まえれば、暗記偏重だからダメだったという見方もまた真理ではないわけです。では何が事態を捩れさせていたのか。勉強と学力が直結しにくくなっていた本当の原因は何なのか?それを探るためには一度視点を高く持ち、勉強という迷路全体を上から俯瞰して見渡す必要がありそうです。何がどう将来と繋がっているかを理解すれば、これまでの何がいけなかったのかも、これからどちらの方向に進めばいいのかも見えてくる。この本ではその視点を、あわよくば俯瞰の位置からさらに鳥瞰できる高みまでエスコートすることを目指しています。
02. 「人はなぜ学ぶのか」
これは私が高校に入学して初めて書いた(もとい、書かされた)小論文のタイトルです。題材は何でも良かったはずなのに、当時の私が直感的に選んだテーマがこれでした。
担任からも匙を投げられ親からも誰からも期待されていなかった中で迎えた高校受験。”裏ワザ”という名の戦略を使って成績下位から1年で勉強を追い上げ、無事にトップ公立高への合格を果たした私は、この下剋上体験をした「のに」なのか「だからこそ」なのか分かりませんが、胸の奥にモヤモヤしたものを感じていました。
当時はまだ「学び」と「勉強」がどう違うかなんてことに気付けていない時期でしたから、この時の自分が感じていたのは
「どうして勉強なんてしないといけないんだろう?」
という疑問だったように思います。
でもそんな小論文の課題があったなんていう記憶を思い出すのはそれから10年ほどが過ぎたある日、実家の建て直しを前に自室の整理をしていた時でした。何やらゴソゴソやっていたら、応援団の学ラン等と一緒にこの小論文などの懐かしい遺物が収納の奥から続々発掘されたというわけです。
過去の自分がこんなタイトルで小論文を書いていたのだと”知った”時、私は自分の人生を賭けて取り組むべきテーマが、やっぱりこの「勉強」だったのだと悟ることになります。なぜならその小論文と再会した時の私は、既に勉強戦略コンサルタントとして仕事を始めていたタイミングだったからです。。。
「勉強」「学び」そして「教育」。これらは学校教育制度下における最も重大な3大テーマでありながら、一方では最も理解されていない3つの謎とも言えます。解いてもいいし、解かなくてもいい。しかし解いた者には心の平安とその先を生きるための武器を、解かざる者には混乱と苦難が与えられる、そんな、人生に付いて回る永遠のテーマがこの3柱だと私は解釈してきました。
別にそれは英数国社理の勉強を真面目にやれ!といった話ではありません。勉強するのかしないのかという、根本的なところから考えていただくための予備知識が誰にとっても必要ではないのか?という、これは問題提起です。そしてその予備知識である
・勉強とは何か
・学びとは何か
・教育とは何か
・努力とは何か
・やる気とは何か
など、勉強にまつわるありとあらゆる要素に可能な限り触れていき、不遜ながらもそこに共通見解を形成したいというのが、この本で成し遂げたい野望です。
曖昧模糊とした流れの中で、しっかり己を打ち立てて自力で漕ぎ続けられる人もいます。その一方で、方角も分からず何をすべきかも見えず、ただただ波に翻弄されて息苦しく過ごす人もいる。私はどちらかというと、その後者の人たちに道を示したい。何が何だか分からないうちに果ても見えない大陸に投げ出され「さぁ、あとは自力で頑張って!」と言われて生き残れる準備がありますか?誰も「準備はいいか!?」なんて言葉はかけてくれません。残念ながらあなたにも私にも時間はないのです。だからこの本の表紙にこの言葉を添えました。
Si vis pacem, para bellum.
03. エピソードゼロ
これから本題に入っていく前に、私の背景を少し説明させて下さい。「勉強のプロ」を自称する人間が如何に生まれたかという、この本の”価値”に関わる話だからです。
私は熊本市出身でありながら、父が転勤族だった関係で幼少期から小学5年生まで関東を転々としていました。小学校低学年から塾に通うのが当たり前の環境の中、中学御三家受験のため周囲と同様、四谷大塚に通い始めたのが小学3年生の時。しかし小学5年生の時に熊本に転校となり、初めて”地方”を体験した私は、塾に通うのが特別とされるような、関東とは真逆の環境の下、熊本大学教育学部附属中学校を受験することになります。
その後、熊本高校、鳥取大学医学部(1年次中退)、中央大学法学部(棄権)、千葉大学工学部の合格、卒業を経て、千葉大学大学院融合科学研究科2年次中退という遍歴を辿り、その途中、大学受験の前に4年間の浪人生活も体験して、稀有なことに、予備校、仮面浪人、寮生活、自宅浪人という浪人生活4パターンをフルコンプリートすることができました(自慢にならん)。
千葉大学在籍中には、2023年で12年目に入ったL&S Consulting 株式会社を起業し、友人の協力の下、今のブレイクスルー・アカデミーの前身となる私塾を立ち上げました。起業コンサルタントの方にマンツーマンのコンサルを受けるため、東京ミッドタウンにあるリッツカールトンホテルのラウンジに通っていたのもこの時期です。土日はディズニーキャストのバイトに勤しみ、個別指導塾のアルバイトもしながら、大学4年間でアメリカ、香港、ニュージーランド、カナダを外遊。ディズニー好きが実を結び、普遍教育の授業提案コンテストで最優秀賞を受賞して、400名以上の在校生を前にプレゼンをさせていただく機会にも恵まれました。千葉県の青少年健全育成プロジェクトにヘッドリーダーとして参画、条例策定委員会にも所属し、その傍らで就活支援のイベントを開催したりと、とにかく浪人4年分の遅れを取り戻さんと必死に学生生活を謳歌したものです。
その後も
・『金持ち父さん貧乏父さん』の著者 ロバート・キヨサキ氏
・世界一の投資家ウォーレン・バフェット氏の一番弟子 メアリー・バフェット氏
・Appleの共同創業者 スティーブ・ウォズニアック氏
・Youtubeの共同創業者 チャド・ハーリー氏
・マーケティングの神様 神田昌典氏 など
といった錚々たる方々とお会いする機会に恵まれる中で、自分の使命と生き方を抉るように模索し尽くした私は、勉強戦略コンサルタントという独自の職業を定義し生み出したことで、当社のアイデンティティを確立させ今に至ります。
この通り、私の背景には、
・関東と地方の両方の空気を知れた体験
・小中高大と続くレールの上での中学受験、高校受験、大学受験、大学院受験の経験
・それに伴う多くの塾への通塾経験
・医学部、法学部、工学部への合格実績
・4パターンの浪人生活
・勉強嫌いから、自分を変えることで勉強のプロへと転身した経験
・就活支援イベント、キャリア支援イベントの開催
に加え、逆にそのレールから降りた先での
・家庭教師、塾講師、進学塾社員としての経験
・私塾の立ち上げ
・起業家としての立場から見た「勉強」
・教育系コンサルタントとしての10年程の実績
・学歴の有無とは全く関係のない成功者たちとの出会い
などがあります。「勉強」というテーマそのものを内からも外からも、酸いも甘いも体験し尽くし、それでいて教師でも塾屋でもない立場から10年以上も関わり続けている人間は正直かなり稀なのではないでしょうか。勉強の価値も重要性も、そしてそれと同じくらいに勉強の無意味さや不毛さも理解しているからこそ、お話できることがあると思うのです。
04. 学力の、その先
”勉強を教える”という場合、そこには英数国社理の個別の問題の解き方を教えるものと、勉強のやり方自体を教えるものがあります。ただ私は、さらにその根底にある「勉強のルール」から教えることを試みました。モグラ叩きのように、問題が噴出する度にそれら1つ1つに対処するよりも、根本原因そのものを叩いた方が解決が早く、同じような問題が再燃しないと考えたからです。
ではその「根本原因そのものを叩く解決法」とは何でしょうか?それは
子どもたちに自分で学ぶことができる力を身に付けてもらうこと
です。この「自分で学ぶ力」こそがこの先「問題解決能力」と呼ばれるようになる、どんな生き方をするにしても必要な”生き抜く力”の核となるものです。今回はこの「勉強」というテーマを一緒に攻略していただき、自分のプラスになるように変えていただきたい。その過程で、問題解決能力そのものも併せて習得してもらおうというのがこの本の狙いです。
勉強に関する問題は、実は想像以上に根深い。ただひたすらに勉強を頑張れば済む話でもありません。子どもたちは今、これまで以上に学校教育制度と受験制度の間に挟まれて訳の分からない状況にあります。勉強と学びと教育がごちゃ混ぜに語られ、自分が将来のために一体何をどうすればいいのかが見えにくくなっているからです。
そこで私は、このもつれにもつれた複雑な状況を、まずは丁寧に解きほぐすことを提案したいと考えています。勉強とは何か、学びとは何か、教育とは何かということを1つ1つ分けて、それぞれをまず理解するのです。そうやって、今自分が何をさせられているのか、この先何をどう考えればいいのかを理解しやすい状態を作ってから、整理された頭で情報を吟味し、未来を模索する方が、色々なことがスッキリ見えてくるからです。
ただそんなことを言われても、明らかに面倒臭そうな作業に思えますよね。本当にそんなことが必要なのか?と思われるかも知れません。でも私は、むしろ今それをしなければ手遅れになってしまう、とさえ思っています。なぜなら国家の根幹を成すはずの人材育成機関「学校」が、かつてないほどの機能不全を起こしているからです。毎年毎年「もっと伸びるはずだった人材」が瑕疵状態のまま大量に卒業させられ社会に輩出され続けている。この現状は明らかに日本という国にとって致命的な機会損失なのです。ここに一刻も早くブレーキを掛けねばならない。私の強烈な危機感はここからもたらされています。
05. 今起きていること
今、公教育そのものが大きく揺らいでいます。
最近特に話題に挙がっている外側の問題が、不登校児急増の問題です。
全国で不登校を選択する小学生中学生が急増しています。その割合は全在校生徒数から計算すると1.7%に過ぎないとも言えますが、数で言えば2023年10月時点で約30万人に及んでいます。無視をするにはあまりに膨大な規模です。
彼ら学校に行かない選択をした子どもたちの決断は、学校教育制度が決壊しかけのダムのごとき状況にあることを示唆しています。各所にできた亀裂から漏れ出した水、それが彼らです。そしてこれは何かの始まりに過ぎません。
小学生中学生はまだ義務教育ですから、仮に不登校になっても、そのシステム上多少の手心が加えられますが、これが高校生となると不登校者には容赦ない厳しい対応が待っています。もはや義務教育ではない高校生は、不登校状態になると間もなく「留年」か「転校」かを迫られることになるのです。そこで転校先としてその需要が伸びているのが通信制高校です(実はこの本は、先日私が登壇させていただいた「通信制高校からの大学進学」というイベントをきっかけに執筆を決めた経緯があります。)。
ただ、小学生中学生の不登校の子たちにしても、通信制高校に通う高校生にしても、彼らはその決断の先で新たな問題に直面することになります。その1つが正に今回取り上げる「勉強」の問題です。
学校に行かないという選択をすること自体は構いません。ただ、それが勉強から離れてしまうきっかけになることが懸念されます。勿論、勉強が全てではないし、勉強よりも大切なことは沢山あるでしょう。ですがそれが、学校のみならず勉強までをも放棄していい理由にはなりませんし、勉強を放棄した代償を補い切れる確証があるとも思えません。我が子が勉強をほとんどしないまま毎日を過ごすことに一片の不安もないという保護者はほとんどいないでしょう。なんとなく心のどこか、頭の片隅には引っかかっていて、いつかどこかで勉強の問題と向き合うことになるだろうな、と思っていらっしゃるはずです。であれば、それは早ければ早い方が良い。
それがなくても、学校の内側の問題として、高度理系人材が圧倒的に不足している状況があります。これは単に少子化の影響というだけではなく、そもそも生産性の高い人材を数多く育成し輩出するという任務に失敗しているということです。現に日本では、過去25年に渡って実質所得が下がり続けています。お隣の韓国にも平均所得も最低賃金も抜かれている。2015年には平均賃金が抜かれ、一人当たりGDPが抜かれたのは2018年のことです。IMD世界競争力センターが公開している分析データによると、日本の国際競争力は対象65カ国中35位と過去最低を記録しました。これはアジア14カ国中11位という結果も伴っています。
加えて、2022年に世界7カ国の17~19歳の若者各1000名を対象に行われた意識調査では、日本の若者たちの内向き、下向き、後ろ向きな思考が露呈される形となりました。これは日本の未来への不安の表れであり、ある意味で警鐘とも取れる内容です。
こういった現実を見て、それでもあえて解決の糸口を勉強に絞ってお話しするのは、それだけ子どもたちにとって「勉強」というテーマがあまりに大きすぎるからです。
06. リアル
詳細は本文に委ねますが、子どもたちは勉強を通して自分を評価する節があります。成績で自分を推し測り、進路を模索し、たどり着けそうな未来をその成績の延長線上に何となく”予想”してしまう。勉強を通した経験が自分の能力を知る指標になり、成績の優劣で頭の良し悪しや能力の高低を比較して、将来の自らの可能性を想像する。勿論ここには多分に思い込みを含んでいるのですが、子どもたちは無意識にそう考えてしまうところがあります。これは子どもたちの経験が浅いからではなく、そもそも勉強とは何かということが見えていないからです。
一方で、勉強への悪い側面からの反動でしょうか、「勉強なんて後からどうにかなる。それよりももっと大切なことがあるよ!」という意見にも懸念があります。
「勉強はいつでも取り返せる」
そう言わざるを得ない状況もあると理解した上で、あえて現実的なことを言わせていただくと、勉強の価値に気付いた時に一気に遅れを取り返すことは、そこまで簡単なこととは言えません。不可能ではありませんが、不可能ではないということと、何とかなるから大丈夫!というのとは意味がまるで違います。小学校、中学校、高校の12年間分を一気に取り戻そうとするのは、正直相当キツいし重い。少なくても1年2年で済む話ではないでしょう。
勉強問題の当事者である子どもたち学生はまだ10代。もし彼らが勉強というものへの理解をハッキリさせて、適切な努力ができるようになれば、彼らは勉強によって選択可能な選択肢の全てにおいて、本来の可能性を十分に発揮し生きていくことができるようになります。「勉強とはこういうものだ」という理解がそこにあれば、今勉強がきっかけで自分の可能性を見失いかけている人も変わっていけるのではないか。少なくても、勉強で辛い思いをしているその大変さを、幾分か緩和させてあげられるのではないか。勉強をきっかけに抱くその漠然とした将来への不安も、解消してあげられるのではないか。
それに今、熱意ある方々が、産官学公教という大システムを構築して連携し、全力で知恵を絞って、幾度も話し合いを重ねながら、子どもたちの未来のために必死に現場を変える努力をされています。凄まじいスピードで起こる技術革新によってどんどん変質変容していく社会状況の中で、今の子どもたちが安心して学べ、かつ社会に出る時には自分の力で生き抜いていけるよう何を教育によって残していくかを、真剣に議論し、環境を整えようと動いて下さっている方々が沢山いるのです。
しかし、だからと言って、子どもたち学生は、その成果を座して待っているわけにはいきません。私たちは私たちで、できることから始める必要があります。では今できることとは一体何か。それは一人一人が力を手にすることです。
でも、どうやって??
その「どうやって?」を徹底的に追求し、具体的な解決法を提案しつつ、子どもたちに自分で学べる力を身に付けてもらおうというのがこの本の目的です。
ん~でも、この本を読んだところで、自分も本当に頭が良くなるんだろうか?本当に、この先自分で勉強できるようになって、将来自分の好きなことで生きていけるような自由を手に入れられるようになるんだろうか、、、
それは誰にも分かりません。それは勉強に困っていない、成績が優秀な人たちも全く同じ条件です。誰も、何の保証もない中で生きています。やってみたらできるかも知れないし、できないかも知れない。それは本気でやってみなければ分からない未来です。
ただ、確実に言えることがあるとすれば、何事においても、「自分にそれができるかどうか」と問うている間は、一生答えは出ないということ。自分に問うなら常にこうして下さい。

結局、やってみた者にしか、その先の道は拓かれないということなんですね。
重要なのは言葉の定義です。その言葉が一体何を意味するのかを明確に理解することが何より重要であるということだけは、是非この瞬間にご記憶いただけたらと思います。
さて、長い前置きもここまでにして、そろそろ真実の扉を開きに行きましょう。安心してこの先を読み進めて下さい。勉強に関するモヤモヤした気持ちから解放されたい全ての人に、この情報が届くことを強く願っています。
『勉強のルール』[もくじ]
はじめに
[第1章] 勉強の正体
”当たり前”の終焉
歴史はかく語りき
『呪術廻戦』に学ぶ問題解決の極意
私が配りたい2つの武器
スマートな成績優秀者
ミックスジュースとブラックスワン
デュアルシステムからハイブリッドシステムへ
勉強とは何か
必須の勉強、特化の勉強
三角関数とか大人になっても使わないじゃん
頑張っているのに成績が伸びない理由
努力とは何か
実る努力の三原則
頑張るとは何かー勉強をギャンブルにしないためにー
効率とは何か
記憶力とは何か
計画とは何か
計画倒れがほぼ100%起こるワケ
戦略とは何か
[第2章] 学校教育の正体
手段の目的化
フリースクール発言の是非
義務教育の正体
漂えど沈まず
教育とは何か
日本の教育制度
多様化する教育の実態
成績とは何か
偏差値とは何か
成績の上げ方
テスト
「テスト頑張ってね」の誤謬
因果関係と相関関係
トップ公立高に逆転合格した裏ワザ
学校の成績の正体
「成績伸ばしてどうするの?」
頑張っても伸びない時の唯一の解決策
成績表の意味するもの
プロセス評価とプロダクト評価
「個別最適化」がさらなる格差を助長する
「一人も取り残さない教育」が孕むリスク
[第3章] 勉強の常識を疑え
あなたが勉強する意味
一と全
未知を知るための情報
何年勉強しても英語は話せません!
学びとは何か
勉強と学びの違い
メビウスの輪
勉強を好きになるな
勉強が嫌い→成績が良い!?
考えるな!覚えるんだ!
[第4章] 勉強戦略の骨子
受験戦略[総合型選抜編]
総合型選抜戦略最大の合否のキモ
量か質か
勉強の本質
「間違えること」こそが勉強
パラダイムシフト
頑張ったら負け
能力とは何か
頭の良さとは何か
[第5章] 脳の本性
嫌々勉強するくらいならしない方がマシな理由
脳の基本的な性質
10000年前の脳
エビングハウスの忘却曲線
「もう受験勉強終わりました」
「受験勉強いつから始める」という愚問
”成績優秀者”をインストールする方法
記憶のメカニズム
睡眠時間は削ってはいけない
勉強効率を飛躍させる方法
眠い時の対処法
TIME DESIGN -記憶のゴールデンタイム-
[第6章] 物事の本質
コペルニクス的転回
全てはココから始まる
IRACサイクル
集中力の正体
集中状態の多様性
頑張らずに結果を出す
ストレス
成績間における破滅的格差の要因
「ウサギと亀」の勘違い
頑張ることと結果は直結しない
学習性無気力という病
まずはその穴から出よ
脳内にある2つの回路
論破王ひろゆきの戦略
[第7章] 自分の変え方
人は変われるのか、変われないのか
自分の変え方
ナポレオンマインド
コンフォートゾーン、ホメオスタシス、スコトーマ
一度上がった成績が元に戻るワケ
90点取れたら嬉しい?
心理的盲点
潜在意識の使い方
流れ星に3回唱えると願いが叶う理由
[第8章] 現実を捻じ曲げる方法
セルフコントロールスキル
自信とは何か
時の流れを逆転させる
理想の未来の描き方
根拠のない自信
自信≠自分を信じること
無限のポテンシャル
メンタルシステム
3人のレンガ職人
[第9章] 3ヶ月で100点伸ばす勉強法
目標の使い方
確実に目標を達成する人が持っているもの
やる気の正体
やる気スイッチは存在するか
モチベーションのジレンマ
もう一つのやる気
勉強が敵から仲間になった日
現実をコントロールせよ
もう勉強で迷わなくなるための勉強戦略論
勉強戦略コンサルティングの実際①[中学生編]
3ヶ月で100点伸ばす方法
勉強戦略コンサルティングの実際②[高校生編]
あなたはどちらを選ぶ?
[第10章] 英数国社理の勉強法基礎学
数学攻略の基本戦略
数学も暗記だ!
すぐに答えを見なさい
絶対やってはいけないNG行為①
絶対やってはいけないNG行為②
絶対やってはいけないNG行為③
絶対やってはいけないNG行為③[補足]「ただし!」
「理解する」とはどういうことか
解答の落とし穴
計算ミス撲滅委員会
国語攻略の基本戦略
100%の傾聴
古典って勉強する意味あるんですか?
不自由のパラドックス
数学と国語の蜜月な関係
英語攻略の基本戦略
無意味記憶と有意味記憶
いきなり英単語暗記と言う勿れ
やってはいけない英語勉強法①
やってはいけない英語勉強法②
リスニング対策はONとOFFで
英作文攻略はまず王道から
英語力の正体
英語力 ≠ 国際的コミュニケーション力
社会攻略の基本戦略
大学受験では何を選ぶべき?
理解モノが先、暗記モノが後
苦手科目の克服はいつするか問題
戦術は正確によって実施される
[第11章] para bellum
今のあなた=10年後のあなた
「好きな仕事をして生きていく」の意味
鶏口牛後を否定する
「自分らしさ」を定義する
学歴フィルターの教えてくれたもの
努力遺伝子
アベンジャーズ構想
あなたに武器を配りたい
Si vis pacem, para bellum.
おわりに
※本来掲載する予定でした「[第3章]学習塾の正体」については削除しました。ご興味あられる方はデータをお渡ししますのでお気軽にお声かけ下さい。
『勉強のルール』がすべての人に届きますように
かなり長い文章でした。もう一度言いますが、まだ本文に入る前の情報がこれです(苦笑)ちなみにちょっと削りました(笑)どんだけ長いんだよって思われるかも知れませんが、それだけお話ししたいことが沢山あるのです。
勉強のすべてを知れば、勉強で苦しむことはなくなるし、何より勉強で人生狂わされることがなくなります。「勉強で人生が狂わされている」というのが最も最悪な影響です。本当にこれは無くしたい。
これから学校から離脱し、フリースクールやオルタナティブスクール、通信制高校といった他の選択肢を選ばれる人たちも増えていくかと思いますが、安易に勉強を捨てることの無いようにとも思います。勉強はいつでも取り返せる、と言う人もいますが、私にはとてもそうとは思えない。そういう言葉もまた、勉強への不理解が原因で出てしまうものでしょう。でも子どもたちは、嫌な勉強から逃げられるなら逃げたいと思っているはずですから、やらないで済む選択肢を選びがちになる。そして気付いた時にはもう遅い、、、というのが、最も子どもたちにさせてはいけないことだと私は思っています。
そういった意味でも、一人でも多くの方にこの情報が届いて、勉強を真に理解し、人生のために上手く使いこなしていただけたらと思います。皆が勉強の正体に気付けば、本当にこの日本は変わるので!
今回のご通読も、誠にありがとうございました!
まずはお電話での無料相談から!
気になった方、今現在勉強で悩まれている方は、今すぐお電話下さい!代表が直接あなたの悩みにお答えします!
相談内容はなんでもOK。成績が上がらない、志望校があるけど諦めかけている、勉強へのやる気がわかない、勉強の仕方が分からない。きっとモヤモヤがおありかと思います。誰かに相談するだけでスッキリするかも知れません。その”誰か”が勉強のプロであれば、そこに具体的な解決策を教えてくれるかも!?当塾の代表はまさにそんな勉強のプロ!勉強戦略コンサルタントとして12年目の現役コーチです!